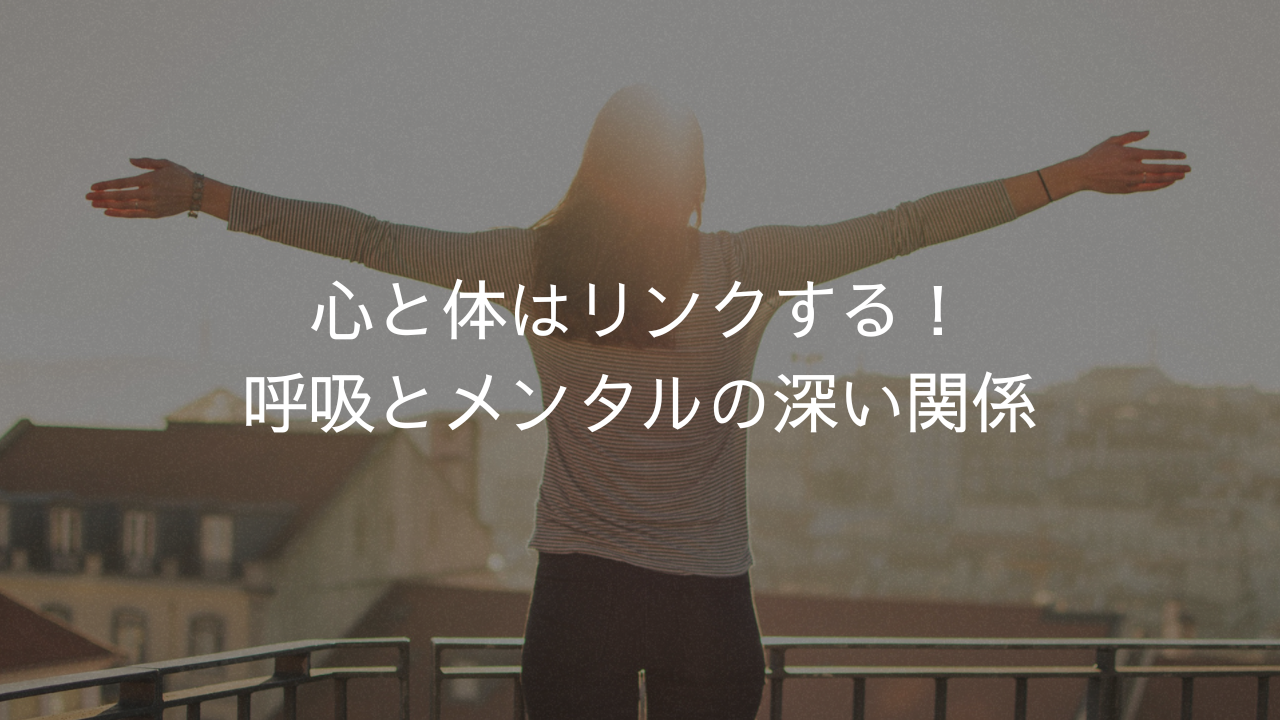私たちが無意識に行っている呼吸。
実はこの呼吸が、心の状態と密接に関わっていることを知っていますか?
また、呼吸が浅いことで出てくる弊害もあります。
私が患者さんの施術をする中で、呼吸の質を改善することで、心身の不調が改善される例を数多く経験してきました。
今回は、現役鍼灸師が、呼吸とメンタルヘルスの関係について、わかりやすく解説していきます。
呼吸とメンタルのかかわり
①自律神経系への影響
呼吸は、私たちの意識でコントロールできる数少ない自律神経機能の一つです。
自律神経は交感神経(活動モード)と副交感神経(リラックスモード)の二つに分かれており、このバランスが心の状態を大きく左右します。
ストレスを感じると、私たちは自然と呼吸が浅くなります。
この時の呼吸は胸式呼吸がメインで、肩や首の筋肉がよく使われるため、筋肉の緊張が強くなってしまいます。
この筋肉の緊張が脳に「危険信号」として伝わり、さらにストレス反応を強化してしまうのです。
一方、ゆっくりとした深い腹式呼吸は、副交感神経を優位にし、心拍数を下げ、血圧を安定させます。
これにより、心身がリラックス状態になり、不安や緊張が自然と和らぎます。
②脳への酸素供給と神経伝達物質
呼吸は脳への酸素供給の役割を担っています。
セロトニンやドーパミンといった、よく耳にする「幸せホルモン」呼ばれる物質の分泌を促進します。
逆に、浅い呼吸や不規則な呼吸は脳の酸素不足を引き起こし、頭痛、集中力の低下、イライラ、うつ傾向などの症状が出やすくなってしまいます。
肺は横に広がるだけではなく、上下にも広がります。
そのため、長時間のデスクワークや、過度の緊張などにより、肩周りの筋肉が硬くなると、肺の動きも制限されやすい状態になってしまい、呼吸が浅くなってしまう原因になってしまいます。
東洋医学から見た呼吸とメンタルヘルス
①気の流れと心の状態
東洋医学では、呼吸は「気」のエネルギーを体内に取り込むために、とても重要なものとされています。
気の流れが滞ると、心身に様々な不調が出てくると考えられています。
正しい呼吸法を身につけることで、気の巡りを改善することが可能です。
②五臓六腑と感情の対応
東洋医学では、「五志(ごし)」という感情が、五臓に対応していると考えられます。
五志が強くなりすぎると、その対応する五臓に影響を与えてしまうとされます。
| 五臓 | 肝 | 心 | 脾 | 肺 | 腎 |
| 五志 | 怒(ど) | 喜(き) | 思(し) | 憂(ゆう) | 恐(きょう) |
肝−怒(ど)
焦りや怒りなどの感情が強くなり、思い悩んだりすることが多くなる。
心−喜(き)
不眠や物忘れが増えたり、汗をかきやすくなったり、顔色が悪くなる。
脾−思(し)
下痢、倦怠感が起きやすくなる。頭がぼーっとする感じや、食欲減退なども起きやすい。
肺−憂(ゆう)
咳、喘息、息切れなどの呼吸器系の症状や、むくみなどの水分代謝が落ちる。
腎−恐(きょう)
全体的に活動のエネルギーが不足しているような感じで、倦怠感や無力感が起きる。また、ほてりやのぼせ、反対に、冷えの症状が出る場合もある。
呼吸を通じて、五臓のそれぞれの働きを調整することで、感情のバランスも整えることができます。
呼吸の質をチェック!
以下の項目に当てはまるものがあれば、呼吸の質に問題がある可能性があります。
- 肩や胸が大きく動く呼吸をしている
- 息を吸う時間より吐く時間が短い
- 呼吸が不規則で浅い
- 猫背や巻き肩の姿勢が強い
- 口呼吸が多い
- 首や肩のこりが慢性的にある
- 疲れやすく、集中力が続かない
- 不安や緊張を感じやすい
- 食いしばりが強い
心身を整える呼吸法
① 基本の腹式呼吸
やり方:
- 仰向けで横になる(椅子に座った状態でもOK)
- 一方の手を胸に、もう一方を腹部に置く
- 鼻からゆっくり4秒かけて息を吸い、お腹を膨らませる
- 口からゆっくり6-8秒かけて息を吐き、お腹をへこませる
- 胸に当てている手はできるだけ動かさないように
効果: 副交感神経の活性化、リラックス効果、不安軽減
② 4-7-8呼吸法
やり方:
- 4秒かけて鼻から息を吸う
- 7秒間息を止める
- 8秒かけて口から息を吐く
効果: 即効性の高いリラックス効果、不眠改善、パニック症状の軽減
③腹式呼吸+胸式呼吸
やり方:
- 仰向けで横になる(椅子に座った状態でもOK)
- 一方の手を胸に、もう一方を腹部に置く
- 鼻からゆっくり4秒かけて息を吸い、お腹と胸を同時に、同じぐらい膨らませる
- 口からゆっくり6-8秒かけて息を吐き、お腹と胸を、同時にへこませる
- 胸に当てている手は、どちらも同じぐらい上下するように
効果:腹式呼吸と胸式呼吸のコントロール
呼吸に使われる筋肉
息を吐く時と吸う時で、それぞれ使われる筋肉があります。
・息を吐く時に使われる筋肉:呼気筋(こききん)
横隔膜、外肋間筋、斜角筋、胸鎖乳突筋など
・息を吸う時に使われる筋肉:吸気筋(きゅうききん)
内肋間筋、腹筋群(腹直筋・内外腹斜筋・腹横筋)など
また、呼吸補助筋と呼ばれる筋肉があります。
それが、斜角筋(しゃかくきん)、胸鎖乳突筋(きょうさにゅうとつきん)、僧帽筋(そうぼうきん)、大・小胸筋、前鋸筋(ぜんきょきん)、肩甲挙筋(けんこうきょきん)です。
これらは、何もしていない安静時の呼吸の時ではなく、深呼吸をした時や、運動時によく働きます。
上記の筋肉のコリや、柔軟性の低下により、呼吸が浅くなりやすくなってしまいます。
姿勢が変われば呼吸も変わる!?
呼吸の質を改善するために重要なことの一つに、姿勢の改善があります。
猫背や巻き肩は、肋骨の動きを妨げてしまいます。
また、食いしばりや歯ぎしりが多い人や、全身の脱力が苦手な人は、緊張や肩や首の凝りのせいで、充分な呼吸を妨げてしまいます。
猫背や巻き肩の悩みを抱える患者さんは、普段治療していると、たくさんいらっしゃいます。
原因は、その人の姿勢や体の使い方、生活習慣などにより様々ですが、上半身だけではなく、全身のバランスが整うことで、確実に呼吸もしやすくなります。
まとめ
呼吸とメンタルヘルスは、科学的にも東洋医学的にも、とても関係が深いです。
現代社会のストレスは呼吸を浅くし、それがさらに心身の不調につながり、悪循環に陥ってしまいます。
そのため、良い呼吸法を身につけることで、心身の不調を改善していくことができます。
まずは基本的な腹式呼吸から始めて、少しずつ、様々な呼吸法を生活に取り入れてみてください。
今日から、呼吸を変えて、心と体が健康でいられるようにしていきましょう!
鍼灸治療、整体施術は、一人一人の症状に合わせた施術が可能です。
是非一度ご相談ください。
また、自身のダンス経験と、西洋医学、東洋医学、スポーツ科学などの視点から、多くのダンス・舞台関係の方々の施術を行なっています。
もちろん、ダンス関係のみではなく、会社員の方々、様々なスポーツをされている方の施術も現在行っております。
詳しくはHPをご確認ください。